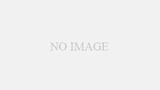今回はビジネスホンと主装置の仕組みについてご説明いたします。
ビジネスホンでは主装置と呼ばれる通話等を制御する本体が存在します。
家庭用電話機と異なり、ビジネスホンには一部の簡易的なものを除いて
必ず主装置が必要となり、電話機とセットで使用します。
主装置の役割は多岐にわたりますが、一般的には外からの着信(外線着信)
を電話機で鳴らし(鳴動させ)て通話を可能にしたり、通話を保留して
他の電話機に繋げる(内線回しする)ことです。
一般的な例で見てみましょう。
①外線着信がある
②電話機が鳴動する
③Aさんが外線着信に応答する(Bさん宛ての電話)
④Aさんが通話を保留する
⑤内線で他の電話機(Bさん)を呼び出す
⑥BさんがAさんからの内線に応答。Aさんは受話器を置く
⑦Bさんが保留されている外線に応答する
細かく分解すると上記のようになりますが、この一連の作業を主装置が
担っています。
家庭用の電話機と大きく異なることのひとつは、複数の回線数を収容して
電話機を増設できることでしょうか。
ビジネスホンでは、回線増設、電話機増設、FAXとの回線共用、構内放送
の利用など様々な機能を利用できますが、このような機能を使うためには
主装置内にユニットと呼ばれる基盤を増やします。
主装置の規格によって増設できるものの数は異なりますので、ご希望の
構成を検討した上で、主装置の規格を選び、必要なユニットを実装して
いくという流れで構成を考えます。
上図は、NTTαNXタイプSの主装置の中の写真です。
少々見にくいかもしれませんが、写真の右側に緑色の大きな基盤が見える
かと思います。こちらはパソコンでいうマザーボードに相当します。
その緑色の基盤と垂直に5枚挿さっているのがユニットです。
一般的に使用されるユニットは主に以下の通りです。
メーカーによって名称が異なりますので通称で表記いたします。
■内線ユニット:電話機を増設するためのユニット
■ひかり電話ユニット(外線ユニット):ひかり電話を直収するためのユニット
■INSユニット(外線ユニット):ISDN回線を収容するためのユニット
■アナログユニット(外線ユニット):アナログ回線を収容するためのユニット
■単体電話ユニット:FAX、受付用電話機等をビジネスホンに収容するためのユニット
■ドアページングユニット:ドアホンや構内放送をビジネスホンに収容するためのユニット
それぞれ、1枚のユニットで使用できる電話機や回線数には上限があります
ので、1枚で不足する場合は複数枚を実装して使用します。
ただし、実装できるユニットにも主装置の規格によって上限があります。
上図では、ユニットを挿す部分(スロット)の空きが2枚しかありません
ので、挿せるユニットはあと2枚です。
また、図の主装置NTTαNXタイプSは、電話機は最大10台まで、単体電話は最大
で4台まで、ISDN回線は最大で2回線まで、アナログ回線は最大で4回線まで、
ひかり電話は最大で4chまでが上限となっておりますので、スロットの空きが
あったとしても上記を超えて実装することはできません。